ともつか治臣「令和のダラさん」
年末年始は積み本をちまちま崩していたが、その中ではこのマンガが一番面白かった。
土砂崩れで祠が崩れたことがきっかけで知り合った蛇神・屋跨斑(ヤマタギマダラ)ことダラさんと、現代っ子のきょうだい(政治的に配慮した表現)の交流を軸とした伝奇コメディ。
ダラさんがなぜ蛇神になったのかという過去編をザッピング的にちょこちょこ挟む構成で、そちらではコメディ色を消している。身体的なギミック以外はちょっと変わってるだけのキャラになりがちなモン娘ものにおいて、モンスターとしての恐ろしさを描写しつつ、人間的な交流も可能ないい演出だと思う。
で、過去編が続き物なのに対して現代編は基本一話完結のコメディのため、ともすれば現代編の方が邪魔になりかねないところ、登場人物の味がとにかく濃いため飽きない。化物のはずのダラさんが周囲に振り回されるという展開が無理なくできている。
連載分では過去編はそろそろ終わりそうなので、その後どういう展開をみせるかも楽しみ。
丸井諒子「ダンジョン飯 10巻」
65話扉絵のうさぎバレリーナマルシルがかわいい。ずいぶん長く続いている気もするけどまだ60話代なんだね。あとカレー食べてる時のファリン(上半身)も。
覚悟を固めたライオスが今までになく格好良く見えるが、それは翼獅子の誘いに一直線に嵌まっていくことでもある。
マルシルの願いを聞いた後の、翼獅子の黒目がゆがむコマ。悪魔の象徴たる山羊の目に変わる瞳に変わるイメージなのかな?

定番だが、全ての人種の命を縮めるような形で願いを叶えそう。とはいえ、翼獅子の邪悪さは、エルフたちによって一方的に語られている面もあるので、今後もう一度ひっくり返されるかもしれない。次巻が楽しみ。
白川雷電「黒鉄の太陽」
朝目覚めると「地下」に落ちていた超能力少女リンと、《太陽》を宿す謎の男クロガネがの冒険活劇。やや詰め込みすぎな感はあるが、それぞれの理由で「天井」を目指すストーリーは一本筋が通っててしっかり読ませてくれる。
石川賢ばりの荒々しいタッチとベタ塗りで描かれる、動きのあるアクションシーンが特徴的。機械と肉が融合したような異形がたくさん登場するのだが、ソリッドさと同時に筋肉の動きが伝わってきてたまらない。特にクロガネの跳躍する様は、上を目指すというテーマとも合致してて見てて気持ちが良い。
あとヒロインのリンの造形が素晴らしいね。三白眼(四白眼?)がいい。瞳の大きさや向いている方向でその場面ごとの意思がはっきりと伝わってくる。普段は地下世界の黒に溶け込む黒のセーラー服に目が映えるって言う構成で、力が解放されると全身が白に染まるという解放感。
地に足の付いた「異端」 筒井賢治『グノーシス 古代キリスト教の〈異端思想〉』
体制批判のごとく血なまぐさい熱狂もなく、殉教指令のごとく凍りつくような冷徹さもなく、単にギリシア哲学や二元論的な世界観を積極的に取り入れてキリスト教の福音を知的に極めようとした無害で生ぬるい運動。表現がネガティブにすぎるかもしれないが、つまるところ、紀元二世紀のキリスト教グノーシスとはこのようなものであったと言っても間違いではない。
いやはや面白かった。最近キリスト教の歴史について興味を持ち色々本を読んでいるが、その中でもピカイチだった。
肉体は仮初めのもので精神こそが人間の本質と見なしそれを貴ぶという考え方は、初期キリスト教以前のギリシア哲学の時代からあった。生に四苦八苦を見いだし輪廻からの離脱を目指す仏教も似通った傾向はあるだろうし、現代日本に生きる我々にも、決して理解できないものではないと思う。
しかしなぜそれが、現世は悪の神が作った悪の世界であるとするキリスト教グノーシス主義に至ったのか。簡単に言えば、ユダヤ教の神とキリスト教の神は本当に同一なのか、という疑問に答えるためである。ヨブ記に表れるような傲慢で人間を所有物として扱う神と、イエスが語る慈悲深き神が同じなのか。アブラハムの子孫を救うユダヤ教の神が、全人類を救うキリスト教の神と同じなのか。そして全能なる神がこの世を作ったのならばなぜこの世に悪が溢れているのか。
もちろんイエスも直弟子たちも我らの神はユダヤの神と同じであると繰り返し述べているし、キリスト教の指導者たちは様々な方法でそれを「論証」してきた。
しかしユダヤ教の神とキリスト教の神は同一ではない、と言ってしまう道もある。それがグノーシスである。ユダヤ教の神(創造神)はキリスト教(至高神)の神のごく一部でしかない。しかもその創造神は自らの不完全性に気づかぬ愚か者であったためにこの世には悪が溢れたが、至高神と我々は愛によって結びついている。よって至高神の存在を認識(グノーシス)し、現世からそこに至るのが救いの道だ、というのがキリスト教グノーシス主義である。
無神論者の浅薄な理解ではあるが、本書を読んでこのように脳内に道筋が出来た。筆者曰く、グノーシスが現世否定の思想だとは言っても、実際の信徒が際立って退廃的・厭世的な行動をとったわけではないそうな。グノーシスの一見とっぴな思想が、狂信ではなく歴史的必然をもった論理的帰結として生まれた、というのが面白い。
33歳独身女騎士隊長。 天原
電子版気になってたけど買ってなかったので、紙の方購入。
小国で姫の護衛やってるタイトルロールの33歳独身女騎士隊長メイルが、男の日照りのブラック職場でアレコレする、ドの付くシモネタギャグ漫画。裸も出てくるけどエロじゃなくてシモ。天原先生は普通にエロも描けるけどエロじゃなくてシモ。
作者本人もあとがき漫画で描いてるけどほとんど一発ネタみたいな内容なのに、毎回ファンタジー世界あるあるでちゃんと膨らませてて2ページでキレたオチつけてて凄い。まあ元々一コマネタめっちゃ上手い人だしね。
メイル以外にも、貧乳色情狂で嫁ぎ先の王子を籠絡して国を乗っ取る王女シルビア、メイルより年上の独身でプライド高くて溜め込んでそうなフローレルのキャラが好き。
シルビアの話は単行本分で一旦落ち着いたんかなと思っていたが、連載分見るとこれからも普通に出てくるみたいなんで安心。これからは連載分も買おう。
藤田弘夫「都市の論理 権力はなぜ都市を必要とするか」
都市の権力は自由にする
以下個人的な要約。
古今東西、国が飢餓状態になったときは、まず食料を生産しているはずの農村から飢える。富山の米騒動、ウクライナの飢餓輸出、アイルランドのジャガイモ飢饉の時、東京やモスクワやロンドンは、少なくとも相対的には飢えていなかった。
何故か。都市に権力があるのに対して、農村には無いからだ。ある農村が飢えたとしても、都市はその政治的、経済的な権力を用いて別の農村から、あるいは国外からも食料を調達し、蓄積することが出来る。それに対して農村には、都市から食料を持ってくるような力はない。
都市が飢える状況というのはただ一つ。戦争に負けて既存の権力が崩壊した時だ。日本ならば戦後すぐの時代、都市の住民が農村まで直接出向いて、物々交換で米を手に入れていたという。通貨が信用を失い、強制的な徴税・徴発も出来なくなったとき、食料を農村から都市に動かす力が無くなるのである。
都市と権力は一体である。権力は都市に住む人々の生活を安全・経済・宗教・教育・医療・文化・情報など様々な形で保障し、その住民の支持を得ることで存続する。生活の保障のためには様々な施設と資源が必要になるため、必要な者は周辺の農村から集められる。農村から都市に移される食料は、農村の自給自足分を超えた〈絶対的余剰〉ではない。都市は都市が必要な分だけを〈社会的余剰〉として調達・備蓄する。
人間が集住すると土地の不足や伝染病の発生など、様々な不自由が生じる。にもかかわらず人間が集住し都市が生まれるのは、都市無くして権力無く、権力無くして長期的な生活保障はできないからである。逆に権力が様々な資源を、特に生存の為に最も必要な食料を都市に用意できないことは、権力の正統性そのものを揺るがしてしまう。
現代ではグローバリズムとナショナリズムの進展の中で、先進国全体が都市に、途上国全体が農村になっている。先進国の中の農村には膨大な補助金が投入される。途上国では首都などごく一部の都市にのみ資源が集められる。社会主義国の計画的な経済の中では都市と農村は厳格に峻別され、資本主義国よりも都市と農村の格差が大きくなってしまうことさえある。
というような本だが、非常に面白かった。
現代においても権力の中心に食があるというのは常々思っていたことである。同じ飯を食らうことが同胞意識を育てる。普段進歩的なことを言っている人間でも、食の話になればとたんに保守的になるのはよくあることだ。
「足りないと言ってもあるところにはある」というのはよくあるが、江戸時代の飢饉でも江戸に押し寄せた農民に米が配られた。彼らが農村にとどまっても座して死ぬだけだっただろう。農村が一つや二つ潰れたところで藩も幕府も対応しない。例外的に対応すれば(そして成功すれば)、義民伝説や名君として美談になり、後世まで語り継がれる。しかし首都で飢えた民が溢れれば、伝染病の発生・治安悪化・暴動への恐れからお上も対応しないわけにはいかないわけだ。
アラブの春でも、首都の住民が政権に反旗を翻せば、例え非武装に近いデモでも政権が倒れる場合があった。一方シリアでは、湾岸諸都市や首都ダマスカスを何とか維持したアサド政権が、長く続いた内戦を制しつつある。都市住民の強固な支持があれば、地方を失っても権力はかなりの間持ちこたえられる証拠だろう。
先進国内部でも、NIMBY施設に都市と権力の論理は見られるだろう。核施設や軍事基地が地方に多く都市に少ないのは、地理的な理由だけではない。そこで生み出されるエネルギーや安全などの資源を都市が享受するためだろう。
本書は後書きで著者本人が書いているように、新書らしく一般向けの平易な文章で非常に読みやすい。理論先行でデータが少ないように見えるので、そこら辺は前著「都市と権力」を読めということなのだろう。
山室信一「キメラ―満洲国の肖像 増補版」 駆り立てるのは理想と欲望、横たわるのは犬と龍
著者山室は、満洲国建国前夜の情勢をゴルディアスの結び目に例える。日本軍は中国北東部の軍閥指導者、張作霖を爆殺するも、息子の張学良は日本軍の陰謀を察知し、権力の早急な掌握に成功。蒋介石に帰順を表明し政治的に安定した事と、折からの漢民族ナショナリズムの高まりにより、反日運動が活発化する。人口と漢民族資本の流入により日系人は徐々に不利な立場に立たされ、日清・日露戦争で血を流しつつ得た権益を失ってなるものかと戦々恐々だった。
また、朝鮮総督府の農地改革で耕す土地を失った朝鮮系の農民が満州に流入していた。金日成が満州で抗日パルチザンを組織していたように、共産主義者や民族主義者の根拠地となる一方、日本に因る侵略の尖兵と見なされ、漢民族とは度々対立していた。元々この地に住む蒙古系・満州系住民の中でもナショナリズムが高まり、増えつつある漢民族に対抗する必要性を感じていた。
「五族協和」のスローガンは、人口では圧倒的に多数である漢系を抑え、朝鮮・蒙古・満州系の指示を得るためのものでもあった。
この複雑に絡まった結び目を断ち切り、新しい国家をつくり上げるダモクレスの剣となったのが関東軍である。1931年に満州事変を引き起こす。当初張学良や蒋介石は中国側の反撃を期待した挑発行動とみなしたため、大きな抵抗もなく全土を征服。かくして満洲国は誕生する。
確かに民族主義が争いを生むというのは一面の真実であったかもしれないし、国民党は自ら掲げる三民主義を実行しているとは言いがたく、軍閥は民衆の生活を脅かしていたのだろう。軍閥を排除し治安を日本軍に任せて民生を安んずる「保境安民」を掲げた于沖漢、日漢平等を信じ民衆自治の成立を夢見た橘樸、王道楽土の建設を目指した現地日系人による満州青年連盟、仏教系政治団体の大雄峯会の面々などは、少なくとも本人の心のなかでは、誠実に満州国建国に関わっていただろう。しかし、そのような人々が、権力の中枢に携わることはなかった。
満洲国には法的に定めのあった国会が最後まで開設されなかった。石原莞爾は国民党や共産党を範にとった一党独裁を目指したが実現しなかった。そのため満洲国は極端な官僚主導国家であり、人口の3%に満たない日系人が官僚の半分以上を占め、しかも主要なポストを独占していた。さらにその多くは本土の省庁から派遣された腰掛けの人員であり、建国の理念に殉じるといった精神からは程遠かった。結局は凡庸で無難な傀儡国家にならざるをえなかったのである。


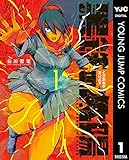




![キメラ 満洲国の肖像 [増補版] (中公新書) キメラ 満洲国の肖像 [増補版] (中公新書)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/313ZrMz7q9L._SL160_.jpg)